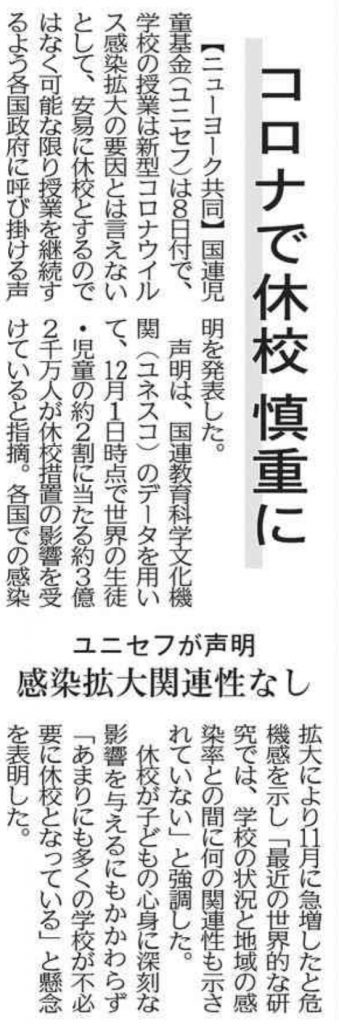だんした:質問題目1、「標準服導入による家計の経済的負担軽減について」です。
最初に、中学校の制服の現状についてですが、筑紫野市内の中学校の制服をどうするかについては基本的に各学校長の裁量に任せており、制服について何か変更する場合は、校長やPTAの方等で構成された制服検討委員会で議論されると聞いています。
次に課題についてです。まず1つ目の課題ですが、まず経済的な負担の面です。現在、学校ごとに制服を導入しているため、デザインもバラバラで価格に差があります。そのため、市内で引っ越しをした場合でも中学校が変われば制服を買い直さなければなりません。また、学校の生徒数にばらつきがあるため、バザーなどでお下がりを買おうとしても生徒数の多い学校では手に入り安く、生徒数の少ない学校では手に入りにくいという問題があります。市の就学援助ですが、制服の購入などの新入学用品費は6万円支給されます。制服だけでなくクラブ活動のユニホームなどまで導入するとなると軽く10万円以上の費用がかかり、「貧困家庭の子どもは好きな部活をするなと言われているように思える」との声もあり、制服に加えて部活動の費用もかかることを考えると経済的負担が重いと言わざるを得ません。
2つ目の課題ですが、制服のデザインや機能面です。現在市内にLGBT(性的少数者)の子どもがいますが、やはりその中で性同一性障害(トランスジェンダー)の子どもが悩んでいるのが、「自分の心の性と違う制服を着なければならないのが非常に苦痛である」ということです。性的少数者への偏見をなくし相互理解を深めるためには、あくまで教育がその中心的役割を果たすべきだと思いますが、このような問題も生じています。また、例えば、女性のスカートは冬には寒く、冷えは身体に良くないということもあり、導入されている制服は体温調節の面からも機能性に問題があるのが現状です。
課題を整理しますと、「各中学校の制服の仕様が異なるため公立中学校間で価格差があること」「学校の人数差のせいで制服の再利用がしにくいこと」「性的少数者の子どもに対して多様性を認めるという観点から配慮が足りないこと」です。
私は、この問題を解決されるように市内で統一したデザインの標準服を新たに導入するべきだと考えます。市内で統一された標準服を導入することで、大量注文により制服業者からの納入価格を抑えることができるので、価格が安くなり、家計の経済的な負担を軽減することができます。そして、市内で制服が統一されるので再利用もしやすくなり、バザーなどで入手もしやすくなります。この制服の再利用は市の掲げるSDGs(持続可能な開発目標)の環境に関する目標にも貢献するものです。その上、デザイン面や機能性を改善し、女子用のスラックスの導入や性的少数者への配慮などもすることができるので、良いことづくめです。
市内の中学校の校長と教育委員会で構成する標準服検討委員会は、市の新たな支出を伴うものではなく、工夫すればすぐに行えるお金のかからない取り組みです。また、新聞報道でもあったように市民の方から要望書も提出されていると聞いています。そこで、私は、教育部長、中学校の校長に問いたいです。家計の経済的負担の軽減や性的少数者の子どもへの配慮をこれ以上ないというくらい全力で行なっているか。このような観点から質問を行います。
そこで、質問項目1、「標準服検討委員会を設置するべき」ではないでしょうか。執行部の見解を求めます。
教育部長答弁
制服の選定方法につきましては、教育委員会が一律に決めるものではなく、各中学校において、保護者代表、教職員代表で構成する「制服検討委員会」が設置され、生徒、保護者、教職員の意見も参考にしながら、各中学校が目指す教育方針や伝統文化等を重んじて、総合的に判断し決定されるものであると認識しております。
今後も経済性や多様性を尊重する視点等に配慮し検討がなされるよう校長会等で周知を図っていく中で、各中学校で標準服導入の気運が高まれば、標準服検討委員会等の設置の必要性も考えてまいります。
だんした:項目1について、再質問いたします。「経済性に配慮し検討がなされるよう周知する」とのことですが、「各学校間の制服代に価格差があることについて、どのように考えているのか」と「近隣での標準服の導入状況を把握しているのか」いうことを再質問いたします。
教育部長再質問答弁
各学校の制服検討委員会において、経済性や多様性など総合的に検討した上で、それぞれの制服が決定されておりますので、現時点においては、その結果を尊重しております。また、筑紫地区では、太宰府市が来年度から標準服を導入することを把握しております。
だんした:各中学校の保護者の方々もこの標準服の件は大変注目していると聞いていますので、ぜひ検討をお願いして次の質問に移ります。